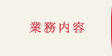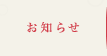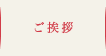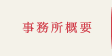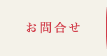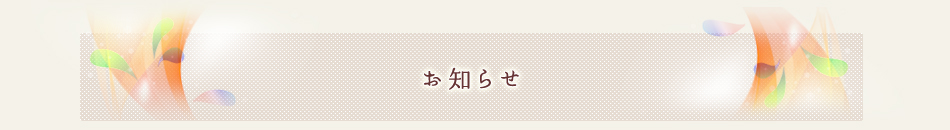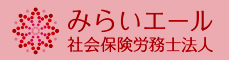- 2025/07/16
- お盆休みのお知らせ
令和7年8月13日(水)~令和7年8月17日(日)まで休業とさせていただきます。
どうぞよろしくお願い致します。 - 2025/06/16
- 2025年6月20日についてお知らせ
2025年6月20日(金)につきましては、職員研修の為、午後から外部コールセンターでの対応とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。 - 2024/12/20
- 2024年12月23日、2025年1月7日についてお知らせ
2024年12月23日(月)、2025年1月7日(火)につきましては、職員研修の為、終日外部コールセンターでの対応とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。 - 2024/12/20
- 年末年始休業のお知らせ
令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)まで休業とさせていただきます。 どうぞよろしくお願い致します。 - 2024/07/24
- お盆休みのお知らせ
令和6年8月10日(土)~令和5年8月15日(木)まで休業とさせていただきます。
※令和6年8月16日(金)は夏季特別営業日とし、終日外部コールセンターでの対応とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。 - 2024/03/27
- 2024年4月17日(水)についてお知らせ
2024年4月17日(水)につきましては、午後より職員研修の為、外部コールセンターでの対応とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。 - 2023/12/13
- 年末年始休業のお知らせ
令和5年12月29日(金)~令和6年1月4日(木)まで休業とさせていただきます。
どうぞよろしくお願い致します。 - 2023/07/12
- お盆休みのお知らせ
令和5年8月11日(金)~令和5年8月15日(火)まで休業とさせていただきます。
どうぞよろしくお願い致します。 - 2023/04/18
- 2023年5月12日(金)についてお知らせ
2023年5月12日(金)につきましては、午後より職員研修の為、外部コールセンターでの対応とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。 - 2022/11/15
- 年末年始休業のお知らせ
令和4年12月29日(木)~令和4年1月5日(木)まで休業とさせていただきます。
どうぞよろしくお願い致します。
- 2025/12/15
- カスハラ対策指針案、就活セクハラ対策指針案を提示
厚生労働省は10日、カスタマーハラスメントの防止に向け、具体例や企業の対応策を盛り込んだ指針案を示した。SNSを使った脅しやSOGIハラもカスハラに当たり得るとした。また、就職活動中の学生らに対するセクシュアルハラスメント防止策などをまとめた指針案も提示した。対面の場面だけでなくSNSやオンラインを通じた場面も対象としている。いずれも改正法が施行される2026年10月から実施される。 - 2025/12/15
- 75歳以上の医療保険料 上限85万円へ
厚生労働省は、後期高齢者医療制度の保険料の上限を来年度に年80万円から85万円に引き上げる案を、12日に開催する社会保障審議会医療保険部会に提示する。影響を受けるのは全体の1.3%程度に当たる年金と給与収入を合わせて年収約1,100万円以上の人。 - 2025/12/15
- ケアプラン 住宅型有料老人ホーム等で有料化
厚生労働省は、重度の要介護者が入居する有料老人ホームの入居者に対して、ケアプランの自己負担を求める方針を固めた。これまで特定施設入居者生活介護の指定を受けていない住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、在宅扱いのため負担はなかったが、重度の要介護者などが入居する一部ホームは、施設としての性質を考え新たに有料化の対象とする。15日の社会保障審議会介護保険部会で、27年度介護保険制度改正の議論をまとめる。 - 2025/12/08
- 病院への賃上げ補助金 国から直接支給
政府は、2025年度補正予算案に計上した医療分野の賃上げ・物価高対策の補助金について、年度内に迅速に届けるため、国公立を含 - 2025/12/08
- 旧姓使用 法制化へ
政府は、結婚で姓を変えた人の旧姓の通称使用を法制化する方針を固めた。戸籍上の夫婦同姓は原則維持し、住民票に旧姓を記載する制度を新設して、行政 - 2025/12/08
- ハローワーク職員 求職者になりすまし企業に応募
都内のハローワーク職員が偽名を使い求職者として2人分登録のうえ9社に応募し、うち4社で採用が決まり、その分を就職 - 2025/12/01
- 国保保険料の軽減、高校生まで拡大へ
厚生労働省は27日、国民健康保険の均等割保険料軽減措置の対象を未就学児から高校生年代まで広げる方針を審議会で示し、了承された。来年の通常国会に改正法案を提出し、早ければ2027年4月の実施を目指す。対象者は約50万人から180万人に広がる見込み。また国保保険料について、年間上限額を来年度から1万円引き上げ、110万円とする方針も固めた。 - 2025/12/01
- 首相、来春闘で昨年並み賃上げを要請
水準の賃上げと、物価上昇に負けないベースアップの実現に向けた協力を要請した。中小企業の成長投資支援や価格転嫁の徹底など、賃上げ環境整備にも取り組む方針も示した。 - 2025/12/01
- 同一労働同一賃金指針、退職金・住宅手当を追加へ
厚生労働省は21日、働き方改革関連法の施行5年後見直しによる同一労働同一賃金指針の見直し案を明らかにした。最高裁判決で待遇差の合理性に関する判断が示された6項目(退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、夏季冬季休暇、褒賞)の追加等を行う方向。見直し案は年内に労働政策審議会の部会で取りまとめられ、年明けに同審議会への諮問・答申を経て告示される見通し。 - 2025/11/25
- 厚労省 農林水産業も労災保険加入義務化の方針
厚生労働省は20日、現在労災保険の加入が任意となっている農林水産業の小規模事業者について、加入義務化の方針を決めた。来年の通常国会で労災保険法の改正を目指す。義務化されると最大約16万の事業者が新たに労災保険に入る見通し。